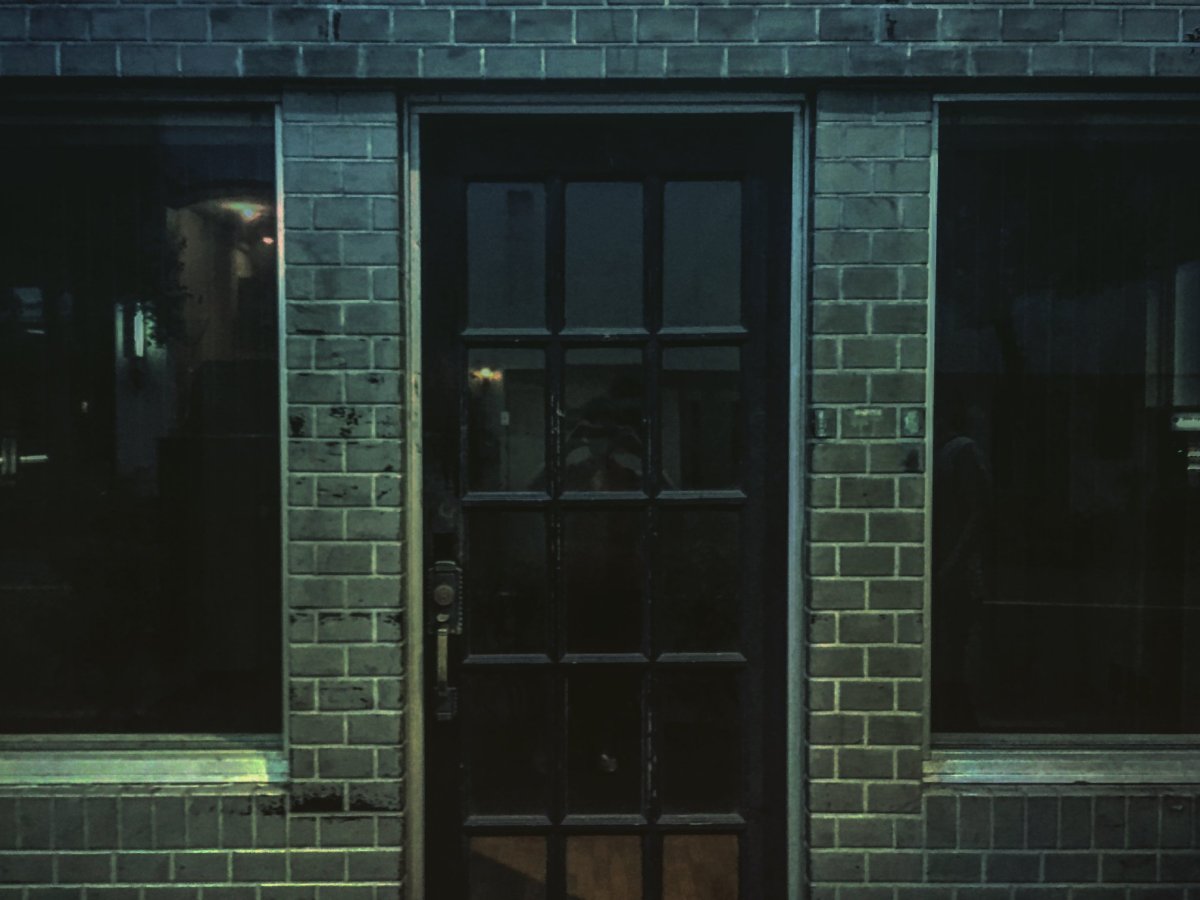先日のチェコナイト、イベント中はバタバタしていてロクに食べないので(飲むものは飲むがw)、終わった翌日・翌々日にチェコモーニング。これまでの会で一番好きな料理、だった。
これだけやっているわけじゃない状況下で、隙間時間を使って、ほぼゼロからの下調べやスライド作りは割と大変だし、実は当日も気を張っているので、単純に「楽しい」わけではないんだけど(実は始まる前は、少し憂鬱、ですらある)、知的好奇心にはかないません。こういったイベントがなければ調べたり、本を読んだりすることがなかった国々のこと、歴史に触れる。写真からはそんなイベントに見えないと思うけど(笑)
ただ、この会をやるにあたって心がけているのは、単純な敵・味方理論、二項対立に陥らないこと。とにかく昨今、イデオロギー的な対立的な図式には辟易していることもあり。こういったイベントをやると、どうしてもその国の良い面だけをピックアップしがち。美しい風景、美味しい料理、素晴らしいアート、人々とのあたたかな触れあい・・・。わざと粗探しをするわけではないけれど、その国に対するステレオタイプみたいなものを相対化するような会でありたいとは思っている。それは私自身の偏見をも含めて。
そんな自分本位でありながら、ゲストの方々を頭も舌も楽しませる宴にする、それがこのイベントのキモである。
以下イベントページでのごあいさつ文より
************************************
第9回目の「コショサン」、無事終了いたしました。チェコを旅したことがある方、チェコのおもちゃを持参してくださった方などもいらして、おしゃべりの尽きない夜となりました。
チェコはとても小さな国ですが、ちょうど中欧の真ん中に位置し、ドイツやオーストリアといった列強国に囲まれていることもあって、中世より政治・文化・宗教・工業の要となっていた地域。中欧で最初に設立された大学も、プラハ大学(1348年)でした。
かわいい雑貨やチェコアニメーション、そして美しいプラハの街並みなどが良く知られるチェコですが、中欧有数の工業地帯をいくつももち、ピストルや戦車など軍需産業も盛んでした(「ピストル」の語源はチェコ語であるとの説有)。キリスト教圏ではありますが、中世より宗教的な争いも絶えず、戦後の社会主義体制下では信者と聖職者間の密告も頻発したこともあって、無神論者が多いことでも有名です。
ごくごく限られた時間のなかではありますが、チェコの歴史や背景をいろいろな角度から眺め、「幻想と現実の錬金術の国」としてのチェコに触れる、そんなことをテーマにスライドショーではお話しさせていただきました。自分のなかでもまだまだ知りたいことがいっぱい、、、今回読み切れなかったチェコ本を携帯する日々がしばらく続きそうです。
お盆時期にも関わらず、近くから、遠くから、夜会に集まっていただいたゲストのみなさん、ありがとうございました。相変わらずイベント中はバタバタしていて写真がなかなか撮れず、ゲストの方々のお写真お借りしましたー。
次回は12月、日本を予定しております!
【KOSHO,SANSHO, TOKIDOKI SALT vol.9 Czech Night】
■お食事 by Ruu Ruu
・ムルケフ・サラート(ニンジンサラダ)
・キセリー・ゼレニナ(キャベツ・トマト・きのこ・パプリカの塩漬)
・スマジェニー・クヴィエタック(カリフラワーのフライ)
・ヴェプショヴィー・ジーゼク(豚肉のカツレツ)
・ブランボロヴィー・サラート(ポテトサラダ)
・ブランポラーク(じゃがいものパンケーキ)
・クネドリーキ(チョコとフルーツ入ゆでパン)
・ペルニーク(ジンジャーブレッド)
■お飲物 by Umi
・チェコビール(スタロプラメン)
・ベヘロフカとスイカのカクテル
・杏と桃のブランデーカクテル
・チェコのオーガニックハーブティ