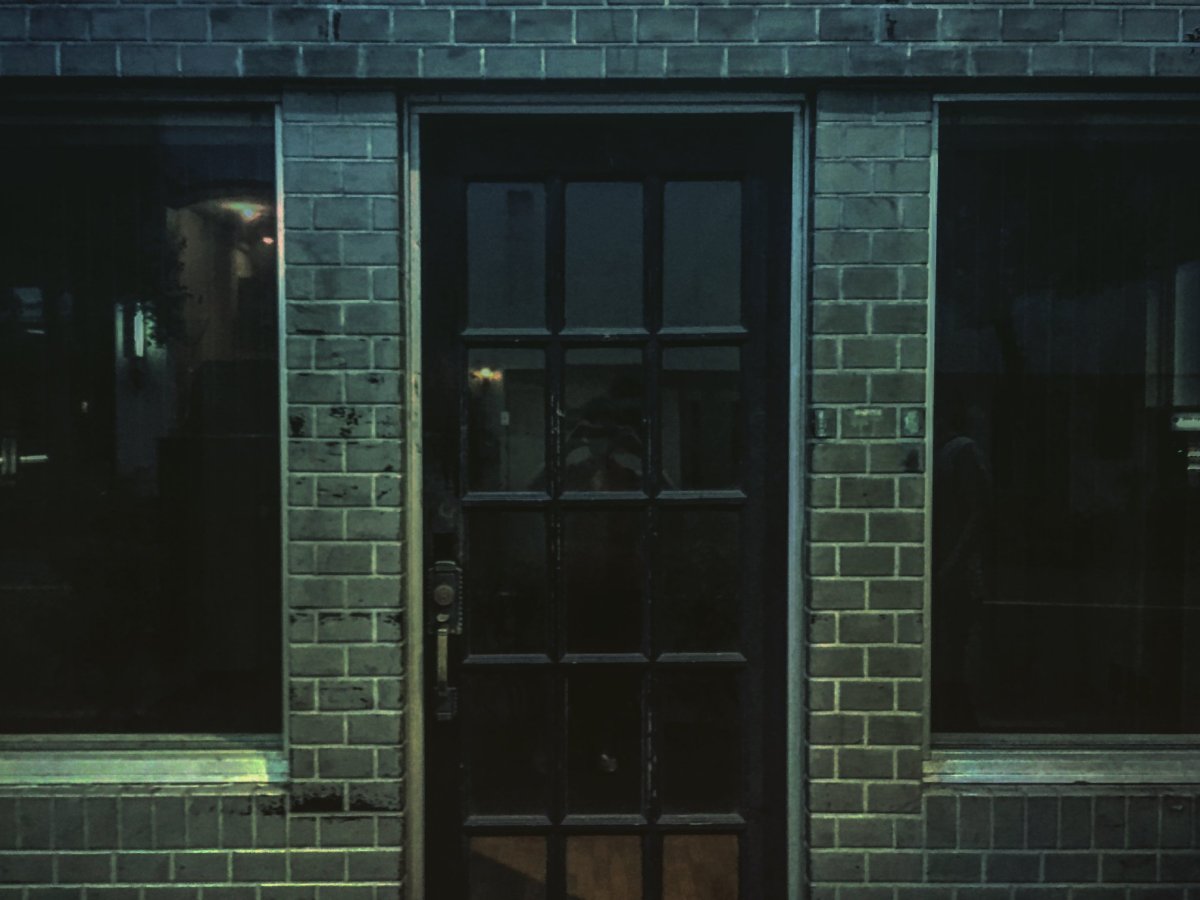2月のブックスドラフトも終わり、3月は通常運転。51回目の今回は心機一転、何か新しいものをと思い、選んだのは韓国文学。最近また第三次韓流ブームがきてるなんて言われてて、文学でもチョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジョン』が話題になってますね(今ふっと紀伊国屋のオンラインショップ見たら「ウェブストアに1790冊在庫がございます」。積んでおりますなー)。
トレンドに乗るというわけではないんですが、いろいろな国の作品を読んでいきたいと思っても、欧米に偏りがち。日本以外のアジアの国の作品を読みたいとずっと思っていたのです。今回はデザインが素敵な晶文社の「韓国文学のオクリモノ」シリーズのなかから、迷ったのですが、私と同世代の作者ということで、キム・エラン『走れ、オヤジ殿』をピックアップしました。
「臨月の母を捨て出奔した父は、私の想像の中でひた走る。今まさに福岡を過ぎ、ボルネオ島を経て、スフィンクスの左足の甲を回り、エンパイア・ステート・ビルに立ち寄り、グアダラマ山脈を越えて、父は走る。蛍光ピンクのハーフパンツをはいて、やせ細った毛深い脚で――。」
残念ながら、まだ韓国文学の多くは文庫化されていないので、単行本(ソフトカバー)となりますが、買って嬉しくなるような、シリーズ全部集めたくなるようなデザインです。これぞ、本の楽しみ!とウキウキと眺めております(今度、好きな装丁の本について話す会とかやりたいなー。ジャケ買いの出会い、失敗談など!)。思えば、韓国映画はちょこちょこ見てるんですけど(not ヨン様)、翻訳韓国文学って読んだことがないかもしれない。先日ようやく初めて食したチーズタッカルビの味を思い出しつつ読みました。
今回の読書会、相方であるカツマタ氏、急遽不在となりました。会場は新大久保。新大久保に来るのは1年ぶりくらいでしたが、いやぁ土曜の夜ということもあって噂通りものすごい人、人、人!しかもその主役は10代~20代の若者たち&観光客。ほんと、竹下通りのよう。。。ここではクレープじゃなくて、チーズハットグですけど。ようやく入れた店・辰家(ヂンガ)で、注文しすぎた料理の多さににウンウンいいながらスタート。
今回の本は短編集だったのですが、タイトルにもある「オヤジ」たちのありようを描く作品が多くありました。それは1997年のアジア通貨危機によって、それまでの家父長的な父親像が揺らぎ、家族の在り方が変容していく、その渦中に作者がいたということが深く関係しています。

急に飛び出して世界を走る父。一人で暮らしている娘のところに突如現れて、そのまま居座り、布団+テレビの前から動こうとしない父。本当は天才でも何でもないむしろアホであるということを受け入れない兄と、そんな長男の幻想を共有するほかない父。久しぶりに会ったのに自分のことに気がつかない父。
「(父は)『お前、父さんの仕事が恥ずかしいのか?』と尋ねた。それまで一度も恥ずかしいと思ったことのなかった父親の職業が、父親がそうした質問をした瞬間から恥ずべきものになってしまった」(紙の魚)
突如、父という存在が何か別のもののように感じられる瞬間。それはもちろん父親の失業=経済力がなくなる、ということだけではなくて(仕事は象徴的ではありますが)、それぞれの関係性によってさまざまなレベルで起こり得ることだと思います。かつてよく言われていたのは、こぶしを使う喧嘩で父親に勝てるようになった瞬間、など。もっとも軽蔑する政治・思想的見解を持っているのを知ったとき、など。
そのときひとはあきれ、時には怒り、そして悲しんだりするわけですが、そこからまた新たな親子関係を築いたり、築かなかったり、築けなかったり。本書の帯には「愛する人へのぎこちない挨拶」とのコピーが掲げられていますが、まさに描かれているのはそんなぎこちない愛(コンビニという空間とその店員に対するぎこちない愛が描かれた作品「コンビニへ行く」も印象に残っています)。
韓国といえばソウルの風景しか浮かんでこない情けなさを感じつつ、いまだあまり知らない隣国韓国に思いを馳せた新大久保の夜、でした。
※この日は、料理に夢中になりすぎたのか、1枚も写真を撮りませんでした…。
**************************
そして突然ですが!わけあって、これから少なくとも半年間ほど、ハードボイルドカツマタ氏は読書会をお休みすることになりました。そのあいだ、どうしようかなぁ…。
→とりたてで意味のない読書会