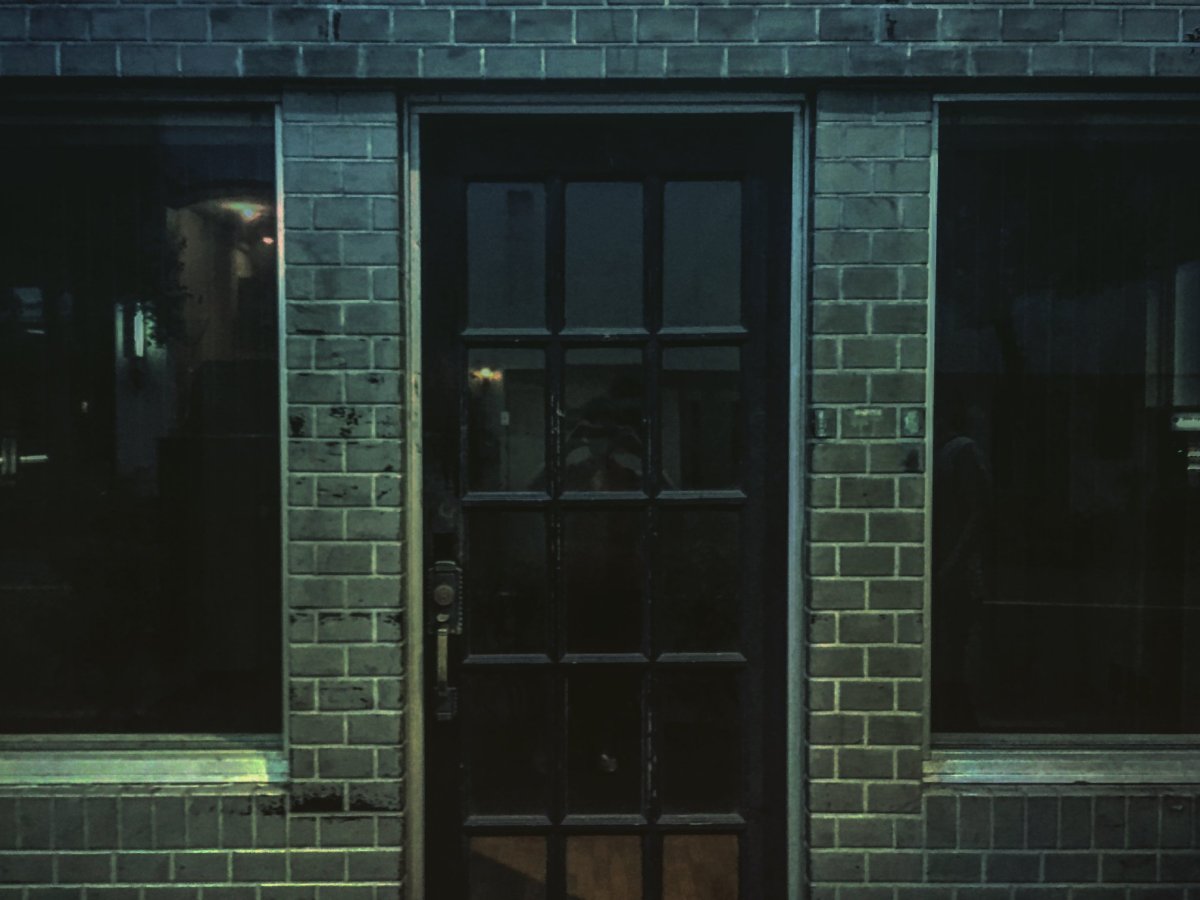48回目となる次回読書会は、嶽本野ばら著『ミシン』(小学館文庫)を読みました。”乙女のカリスマ”と呼ばれていた野ばら氏、映画がヒットした『下妻物語』(2002)が有名ですが、2000年に発表された本作は、野ばら氏の初期衝動が詰まっている小説デビュー作。パラパラっとめくっただけで、圧倒的な洋服への愛や、乙女の生きざまに、心がザワザワしてきます。きっと、私自身の”あの頃”の気持ちがよみがえってきて、懐かしくも、そこに「何か」置いてきてしまったような気がして、切なくなるからかもしれません。。。
仕事柄「服が売れない売れない」とぼやいている私ですが、作中に並ぶブランド名(記号)の数々、「まずはデパートメントに行こう。逃避行に先立ち、買いたいものがあるんだ」なんて文章を読むと、単純に「あの頃は良かった」なんてことは申しませんが、少し泣けてきます。
私は、野ばら氏のデビューエッセイ『それいぬ―正しい乙女になるために』(1998)を読んで、京都の河原町の老舗喫茶「ソワレ」に、フルーツポンチ食べに行ったクチですが、今回の会場も野ばら氏作品にはぴったり?な横浜は関内にある純喫茶「コーヒーの大学院 ルミエール・ド・パリ」。横浜近辺をフラフラしているカツマタ氏は、よくこの店の前を通っていたそうで、「ついに来ましたか!」、と(笑)。

この日は横浜スタジアムで特に催しもなかったようで、到着した19時頃にはすでにひっそりとしていた関内の街。そんな街でぼうっと光っていたのが、今回の会場「コーヒーの大学院 ルミエール・ド・パリ」の赤い看板。表には甲冑が飾られ、赤が基調となった店内には、大理石の壁、きらびやかなシャンデリア、ステンドグラス、そしてなぜか熱帯魚の水槽もあって、怪しさ満点。日本の古き良き喫茶店のありようを感じさせる、ごちゃまぜ感。
そこでページをめくった、『ミシン』。雑貨店で働く”ボク”と、そこに突如現れる全身Vivienne Westwoodで固めた少女との会話なき逃避行「世界の終わりという名の雑貨店」。ファッションブランドmilkをまとったパンクバンドの女性ボーカル”ミシン”と、ミシンに恋し自身もmilkのブティックに通いつめ、ついにはバンドのメンバーになって心を寄せ合う少女二人の物語「ミシン」の2作品がおさめられています。
あらすじからもわかるように、ファッションがポイントとなっている作品。というか野ばら氏にとって(野ばら氏が考える「乙女」にとって)、”お洋服”は非常に重要なもの。私であることを肯定してくれるものであり、そして社会から身を守る「鎧」でもあります。このあたりの「お洋服への愛」が、理解しづらく「??」となってしまった男性もいたようですが、女性参加者には大なり小なり身に覚えがあったようです笑。しかしまぁ、都築響一が『着倒れ方丈記』で撮ったような、お洋服(ブランド)の収集が注目されたのも今は昔。ユニクロやファストファッションの時代を経て、メルカリで売る・手放すことを前提としたブランド買いの今、ここで描かれているような”お洋服への愛”に触れると、隔世の感があります(もっとも、メルカリでやりとりされている服もユニクロが多いようですが。ユニクロが二次流通価値があるという時代、というべきか)。
どちらの物語も、本当は一つである自分の片割れ(ツイン)を見つけた喜びと、でも結局は一つになれない(なれなかった)悲しみが描かれています。「アナタとワタシ以外どうでもいい」という世界はいかにも「箱庭的」だという指摘もあったけれど、実際二人にとっては、周りの奴らは笑っちゃうほど単細胞な「へのへのもへじ」でしかなく、世界なんてどうでもいい(この辺が00年代の”セカイ系”とは異なるところである)。こういう「幼さ」が、ある意味「乙女」の強さであって、大人になるにつれ失われていくものなのかもしれません。実際野ばら氏も2016年のサイゾーのインタビューで「僕の作品って“はしか”みたいなもので、ある年代になったり、ある程度社会経験とかを経たら、醒めていく。通過点なんですよ」と述べています。
サブカルチャー研究の本山ともいえるイギリスでは、70年代から、多くのサブカルチャー研究は声が大きな男性中心の文化しか重要視しないけれど、少女たちはベッドルームのなかで密やかに文化を通した抵抗をしてきたと指摘してきましたが、いかにも夢みがちで逃避的な「乙女文化」は、既存の社会の価値観の拒否・否定であるともいえます。汚くて無教養で美意識のかけらもなくそして暴力的な”not 乙女”な奴らたちなんて知らない!美しいものだけに囲まれたい!その精神性こそが、乙女≒ロリータがパンクと接続されるゆえんでしょう。もちろんそれは、先にあげたように「通過点」であるのかもしれませんが。
「貧乏であることは僕の中で、ちっとも悪いことではありませんでした。しかし貧乏くさいことは諸悪の根源でありました」と書いた野ばら氏、ご存知の通り(?)いろいろあったりなんだりで、今は京都の実家で暮らしているという。少し前のインタビューで、いろいろと周りのものも売ってしまって、印税は月100円ほど…と語っていましたが、それでもどこか飄々としている野ばら氏の今後の新たな展開が楽しみ!ということで、この日の読書会をとりあえずまとめたのでした(笑)。

****************************
【とりたてで意味のない読書会 vol.48】
◆日時:11/24(土)19:00~
◆場所:コーヒーの大学院 ルミエール・ド・パリ(関内)
https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140104/14002242/
◆本:嶽本野ばら『ミシン』(小学館文庫)
https://amzn.to/2ThEho9
◆内容:コーヒーや紅茶を飲みつつ、本の感想について、テーマについてワイワイとお話します。
参加条件:
①開催日までに本を最後まで読めるひと
②話のなかで専門用語を多用したり特定の思想を強要しないひと(わかりやすい言葉で!)
参加費はありません。それぞれの飲食代、実費です。
※第一部は本の話中心に喫茶店で。その後場所を移して、第二部にしけこみます(第二部は有志の方のみ。途中脱出可)。
※年齢性別問わず、誰でも参加OKです。
※「読書苦手な人」「読書嫌いな人」の参加も歓迎します。初回のみ見学オッケーです。参加希望者はコメント、メッセージ、メールに
てカツマタ/サトウまでお気軽に連絡下さい。