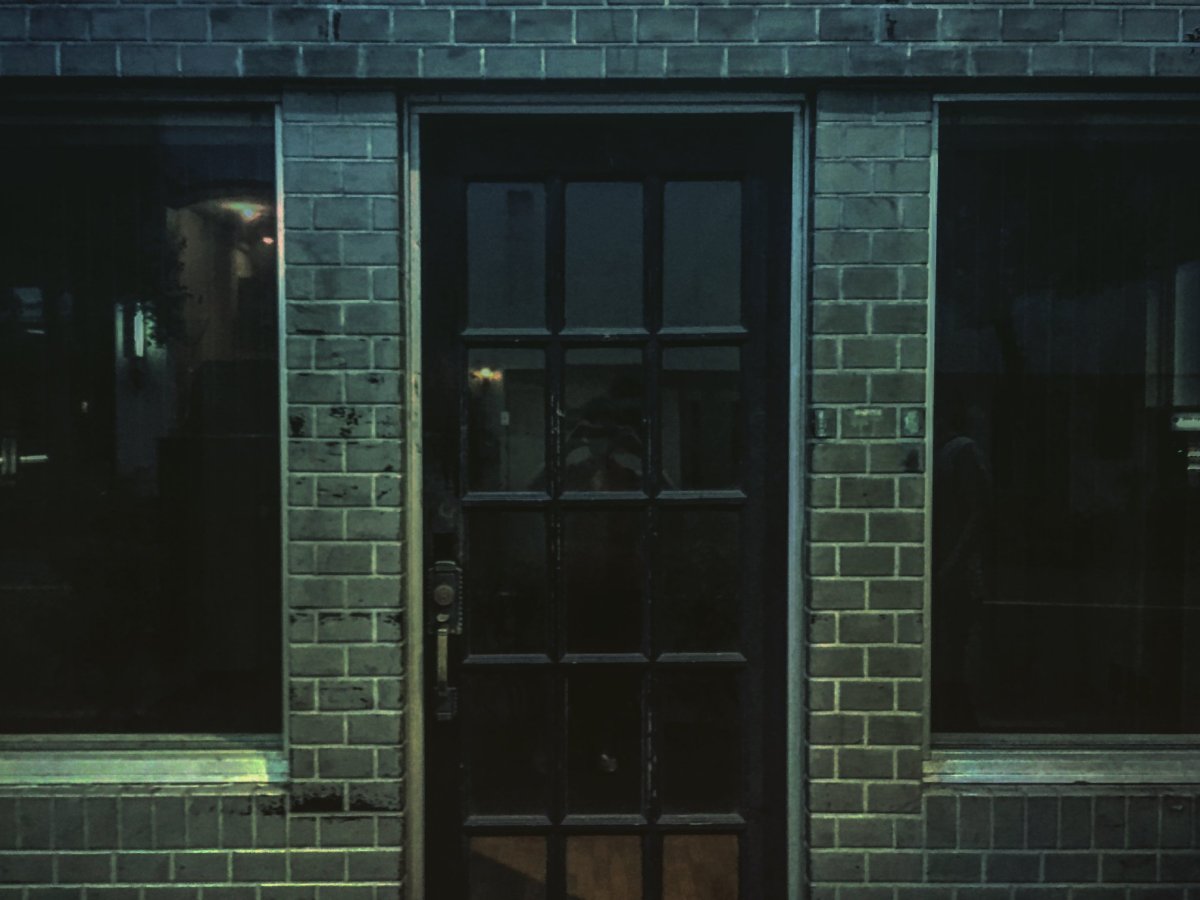今回は、前回の参加者、凄腕イベントプロデューサーA&ANSの矢田さんからのご推薦本、アルゼンチンの作家マヌエル・プイグによる『蜘蛛女のキス』。アルゼンチンで出版されたのは1976年、その後1979年にアメリカで英訳され、1985年にはエクトール・バベンコ監督によって映画化され(アメリカ・ブラジル合作)、主演のウィリアム・ハートはアカデミー賞主演男優賞を受賞している。集英社文庫において日本語訳が出たのは、その3年後の1988年(2011年に改訂版が出ている)。


私は未見だが、映画はアカデミー賞ほかさまざまな映画祭で賞をとっていることもあり、私や読書会周りでは「映画は見ているけど…」という声が多かった本作品、未成年者に対する性的行為で懲役となったトランスジェンダーのモリーナと、政治犯として収容されている革命家のヴァレンティンの(ほぼ)二人しか登場しない。全編にわたって、二人の会話によって物語が展開されていく。

会話といってもその基本となるのは、モリーナがヴァレンティンに話して聞かせる、自分のお気に入りの映画のストーリー。驚くほど細部にわたって映画を描写するモリーナだが、もちろんそれはモリーナの解釈によるものであり、本当のところはわからない。考え方が全く異なるヴァレンティンは、しばしば茶々を入れ、批判をし、耳をふさぐが、どんな「物語」であっても牢獄という閉じられた空間においてそれがいかに貴重で、希望であることか。
監獄(社会から隔離された状況)における文化の貴重さというと、フランク・ダラボン監督による1994年のアメリカ映画「ショーシャンクの空に」(原作はスティーブン・キングの『刑務所のリタ・ヘイワース』)のあるシーンをめぐる、今は亡き父との会話を思い出す。劇中で、のちに脱獄に成功させる囚人のアンディは、監視の目を盗み、図書室から刑務所全館に音楽を流すというシーンがある。それはモーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」からの一曲、囚人たちは突如流れてきた音楽にびっくりし、じっとスピーカーを見つめ聴き入る。刑務所の中で厳かにクラシック音楽が流れるそのシーンは、映画だからこそ説得力のあるシーンであるといえよう(原作にはないようだ)。

囚人には、モーガン・フリーマン扮するアンディの仲間も含めアフリカ系アメリカ人もいるし、オペラなんてものに縁がなかったようなものたちも多いはず。そんな状況における「フィガロの結婚」。ブルース/ソウル至上主義だった父は「こんな音楽じゃなくてさぁ」と鼻で笑ったのだが、父のそんな至上主義にうんざりしていた私は、「いや、そうじゃなくて、この状況(環境)で聴く音楽であるということを考えるべき!」と反発したのだった。20年以上ろくに聴いていなかった音楽、そしてそれが思いがけず流れてきたら、どんなものでもギフトだと感じるのではないか。たとえそれが(私の忌み嫌う)ZARDの「負けないで」みたいな曲だったとしても。
革命に燃えるマッチョで学もある男ヴァレンティンは、夢見がちで自分にとって都合の良い解釈で映画を語るトランスジェンダーのモーリスを最初は軽蔑している。けれどメタメタに絶望に打ちひしがれた状況において、モーリスのポジティブさはやはり救いになる。かいがいしく汚物の処理をしたり、布団や差し入れの果物を分け与えたり。。。安易ではあるが、まるで母のような(しかし「母的」役割をするのはここでも「女役」である)。実はモーリスの背後には大きな力が控えていて、役割をもってヴァレンティンに近づいていたのだけれど、モーリス自身も次第に当初の目的が揺らぎ、ヴァレンティンに惹かれていく。そして二人は慰めあうかのようにキスをしセックスをするのだけど。

今回唯一の男性参加者であり、いわゆる”ノンケ”であるカツマタ氏に、もし自分がヴァレンティンと同じ状況下にいたら、モーリスとセックスするかと聞いてみた。するとカツマタ氏はしばし考えて、「うーん、それはないと思います」と答えた。その返答は尊重しつつも(そりゃどんな状況だって、選び拒否する権利はある!)、リベラルで開かれた考え方のカツマタ氏ですらそう答えるのを見て、私はふと、上記で書いたような(ショーシャンクのある場面をめぐる父との会話で感じたような)極限状態における渇望への想像が、というかそういう欲望も持ち得るであろうと表明することが、男同士のホモセクシャルではとかく難しいのかの、と感じたのだった(ついでにいえばこれは、男同士のホモセクシャルであると同時にホモソーシャルである。男と女であったら二人の友情や愛情のやり取りは、これほど感動的に受け止められたであろうか?)。

2軒目の喫茶店は、喫茶ロジェ
そんな風にいつもよりも色っぽい(?)会話が続いた今回の読書会。喫茶ニットが20時までだったので別の場所へと移動。飲めない方もいたということもあって、今回は2軒目も喫茶店(酒がある、という条件はつけさせてもらったが)に行く羽目になった。テーブル筐体が置いてあるまさにレトロな喫茶店。何も食べていなかたので、数少ないメニューの中からいくつか頼んでみたが、「うーーん。。。」となってしまうまさにレトロな喫茶店。
マヌエル・プイグ『蜘蛛女のキス』(集英社文庫)

ヘクトル・バベンコ「蜘蛛女のキス スペシャルエディション(DVD2枚組)」